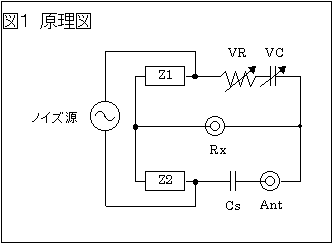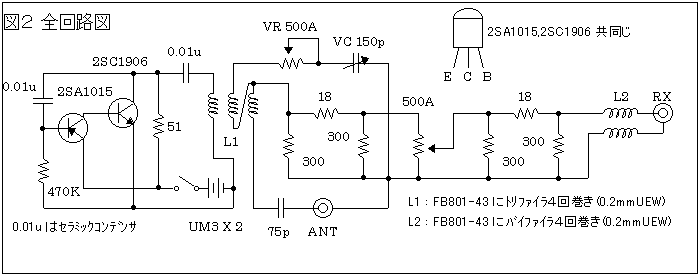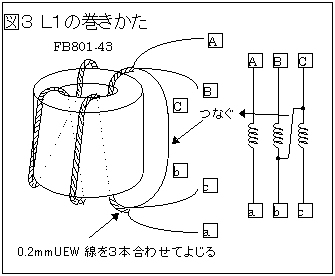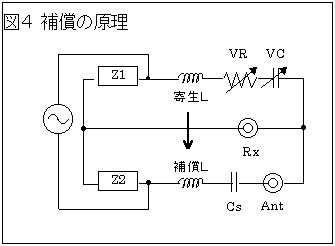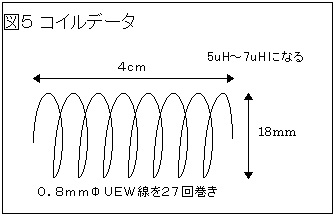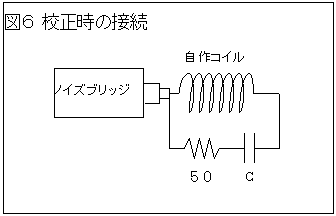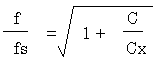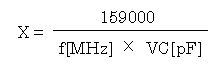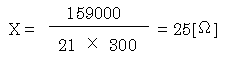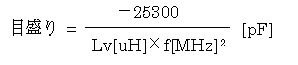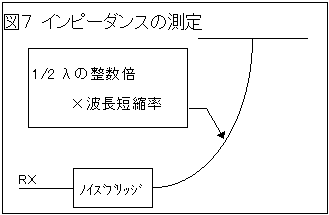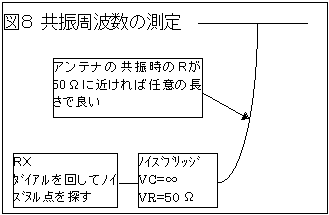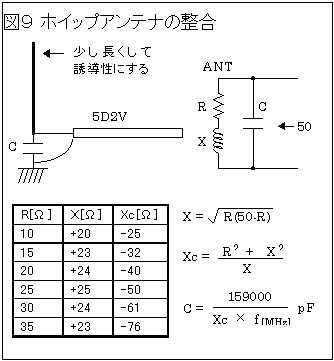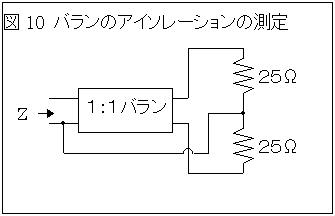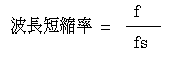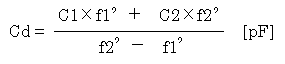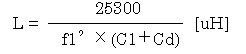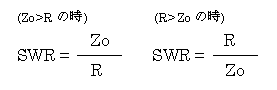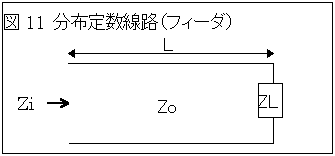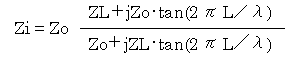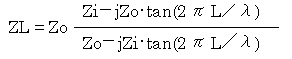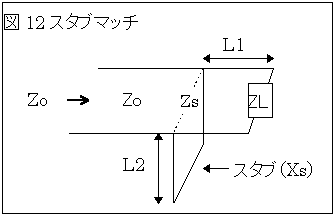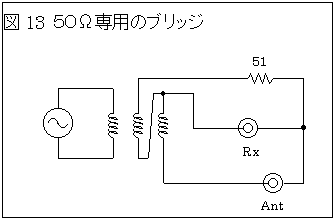ノイズ・ブリッジの製作
Updated on 2000.June.01
この記事は1999年5月号からの高槻アマチュア無線クラブ会報誌に、
5回の連載で掲載していただいた原稿を、HTMLに変更したものです。 |
「ノイズ・ブリッジの製作」
JE3HHT 森 誠
○はじめに
アンテナの調整をする際、昔からディップメータやインピーダンスメータ等が使われてきました。私も長い間これらの測定器のお世話になりましたが、結婚すると同時に期せずしてアンテナ・アナライザMFJ259が使えるようになりました(嫁はんが嫁入り道具として持ってきた!)。これの使い心地は抜群で、今までの泥臭い作業はなんやったんやという気になりましたが、唯一の不満はリアクタンスの測定ができない点でした。
つい最近になってリアクタンスが測定できる改良版がMFJから販売されるようになり、何となく悔しい気分になった(Hi)のを機会に、いろいろと検討した結果、比較的簡単に自作する事ができ、今まで使ったことがなかったノイズ・ブリッジを試してみる事にしました。
ノイズ・ブリッジは、アンテナの抵抗とリアクタンス、共振周波数等を測定する事ができ、これ一台だけでアンテナ調整をこなすことができます。
ズバリの参考文献が手元になかったので手探りで作りましたが、簡単な割には好結果が得られましたので、この会報を通じて皆さんに紹介する事にします。
○校正に必要なもの
測定器を自作する場合、それをいかに校正するかが問題になります。より精度の高い測定器を使って校正するのがベストですが、それが利用できないから自作するのが普通ですので、この方法は最初から問題外です。Hi
今回のノイズブリッジは、50Ωの抵抗と、値が判っているコンデンサが数個、また適当なコイルを自作して、実用範囲内の精度に校正する事ができます。測定器としてはテスターとゼネラルカバレッジ受信機(HFトランシーバ)が必要です。
ただし、最初に断っておきますが、私たちが測定器を自作する場合、その精度や経年変化に関しては過度な期待は持たない方が無難です。これはアマチュア用に販売されている測定器に関しても同様の事が言えます。業務用の測定器は極めて高価ですが、そのメインテナンスも含めて、それなりの理由がある事を承知しておく必要があります。
しかし私たちアマチュアの場合、一部の技術系の方以外は、高精度を追求する必要はまったくなく、ある程度の目安として利用できれば十分であると思います。ちなみに嫁はんのMFJは50Ωダミーを測定した場合40Ωと指示します。
○ノイズ・ブリッジの原理
図1にノイズ・ブリッジの原理図を示します。広帯域なノイズ発生装置からの信号をブリッジに供給し、目的の周波数を受信機で受信して、そのノイズが最小(ヌル)になるようにVRとVCを調整すると、その点がブリッジの平衡点となり、Z1とZ2を等しくしておけば、VRとVCの値から、アンテナの抵抗とリアクタンスを得ることができます(もちろん対象はアンテナだけに限りません)。
また逆にVCをリアクタンスが0になる点(VC=Cs)に固定し、受信機のダイアルを回してノイズヌル点を探せば、その点がすなわちアンテナの共振周波数という事になります。
なおVRとVCの合成インピーダンスが、アンテナ側回路のインピーダンスと等しくなるとブリッジが平衡しますので、アンテナ側回路にCsのキャパシタンスオフセットを入れることにより、アンテナがインダクティブでもその逆オフセットでインダクタンスを測定できるように工夫されています。
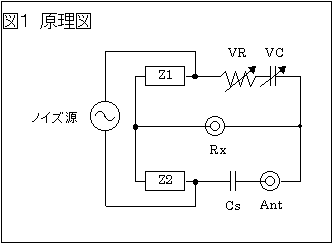
ノイズブリッジでは、周波数の弁別を受信機の選択特性に委ねているので、高周波電源として単一周波数の信号は必要とせず、簡単な広帯域ノイズ発生器が利用できます。一般のインピーダンスメータでは、高周波電源としてディップメータ等を組み合わせますが、ノイズブリッジではそんなもんは必要ありません。
もちろん受信機で受信できる周波数であれば、どこでも測定できますし、送信するという操作がないので免許も不要で、バンド外でも測定できます。ただし市販のアンテナアナライザはメータ直読ですが、このノイズブリッジではVRとVCまたは受信機のダイアルを回してノイズヌル点を探すという若干の手間が必要になります。
昔は受信機にBCL用の短波ラジオを利用していたようですが、最近のHFトランシーバはジェネラル・カバレッジ受信ができるものが多く、この点好都合になりました(トランシーバを使用する場合は絶対に送信しないように!)。
原理的にはいかなる周波数でも測定できますが、周波数が高くなるとノイズの発生が難しく、また内部の部品や配線が持つリアクタンス分も無視できなくなります。更に例えそれらを解決できたとしても、測定そのものにも、それなりの知識と技術が必要です(これは市販のアンテナアナライザを使う場合も同じです)。
今回作成するノイズ・ブリッジの現実的な利用範囲は、概ねHF帯に限られ、50MHzもおまけで測定できる程度と考えておくと良いと思います。
なお日中の7MHzや夜間の3.5MHzでは、いろんな信号が強力に受信されてしまうので、QRMによりノイズが判別し辛くなり測定が少し難しくなります。これはノイズブリッジの持つ最大の欠点です。
○回路図
今回作成するノイズ・ブリッジの全回路を図2に示します。
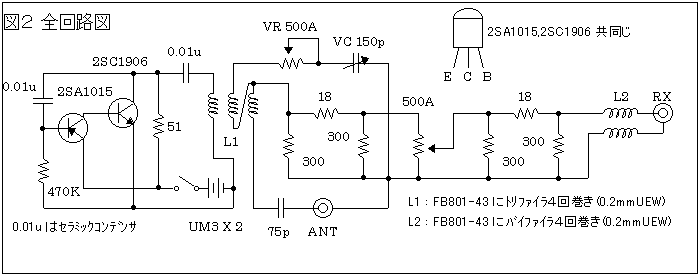
トランジスタ2個で構成される部分では約200Hzのパルス波を発振しており、この信号はVHF帯ぐらいまで受信できるスプリアス成分を持ちます。これを広帯域のノイズ源として利用します。この目的では発振周波数の精度や安定度はあまり重要ではありません。実はノイズ源としてこの回路を使ったのは今回が初めてで、信号が強すぎるのではないかと危惧していましたが、3Vの電池で動作させた場合は思ったほど強くはありませんでした。そこでトランジスタを当初実験した2SC1815から、Ftの高い2SC1906に変更すると少し改善しました。PNP側の2SA1015も、Ftの高い石に交換するほうがFBですが、適当な石が手に入らなかったのでそのまま使っています。使用したトランジスタはすべて共立電子で入手可能です(〜50円)。
なお、現状では3Vの時の消費電流は実測で1.5mAですので、電池はかなり長持ちすると思います。電池に006P(9V)を使うと144MHzでも使用できますが、今回はその周波数を目標にしていませんので、単3二本で使用する事にしました。この程度ならば出力はとても弱く、他への妨害の心配もありません。
ブリッジ回路は差動ブリッジと呼ばれるもので、原理図と見た目が少し違いますが、動作はまったく同じです。Z1とZ2に相当する部分にトランスを使用すると、ノイズ信号の減衰を少なくする事ができます。L1のトランスにはトロイダルコア(フェライトビーズで代用)による位相分波器と呼ばれる回路を使いました。純伝送路トランスとしては働いていませんが、これでも1MHz〜100MHzの範囲で十分な通過特性を持ち、位相誤差も問題にならないようです。実はこの部分は、純伝送路トランスを使ってみたり、50Ωの抵抗2個で分割する方法(原理図と同じ回路)等をいろいろと試してみましたが、平衡の取れ具合等の差はまったくありませんでした。
バリコンには耐圧は必要なく、安価なポリバリコンで十分です。ただツマミの取り付け等を考えると、タイト製のエアバリコン(ニノミヤエレホビーが品揃えが豊富)に分がありますが、高価(1K〜2K)なので財布のひもと相談して下さい。Hi
バリコンの最大容量はリアクタンスの測定範囲と使い勝手に影響しますので、ご自分の好みで適当に選んで下さい。HF帯全域をカバーしたい場合は150pFぐらい、またローバンドを重視する場合は200pF〜300pF、逆にハイバンドや50MHzを重視するのであれば50pF〜100pFが適当です。
私は共立電子で260pFのAM用単連ポリバリコン(200円)を購入して作りましたが、ハイバンドでインダクティブ側のカバー範囲に不足感があるので、別に100pFぐらいのポリバリコンを使ったものも作成してみました。
ブリッジ対側のコンデンサ(75pF)は、使用するバリコンの最大容量の半分ぐらいの値にしておけば、ダイアルの中央でリアクタンス0になります。またこの値は正確である必要はありませんが、セラミックコンデンサは温度特性が悪く、吸湿性も高くて経年変化が激しいですから、できればディップマイカ(共立電子で130円〜180円)を使うほうが良いでしょう。
VRは500ΩのAカーブを使いました。私達が良く使うアンテナのインピーダンスは10Ω〜450Ω程度ですし、50Ωが最も重要ですからAカーブが適していると思います。
このVRにはできれば金属皮膜、手に入らなければカーボンタイプのVRを使ってください(私はニノミヤエレホビーでカーボンタイプを入手)。形状が小さいものはすぐにガリオームになりますので、大きなものを使うことをお勧めします。ただし、抵抗体が巻き線になっているもは今回の用途に向きませんので注意して下さい。
受信機への出力部分には3dBのATT,レベル調整用のVR,フェライトビーズを使ったソータバラン(L2)を入れて有ります。この3dBのATTは、共にインピーダンスを50Ω付近に強制的に整合させて、ソータバランの効きやブリッジの動作を安定させる目的があります。また誤って送信した際のヒューズの役割も少し期待しています。Hi
なお回路図には書いていませんが、校正用に50Ω(51Ω)の金属皮膜抵抗2本と、10pF,82pF,200pFのディップマイカコンデンサ(誤差5%)各1個づつ、また同軸のオスコネクタを2個用意しておいて下さい。
○製作
図3に位相分波器(L1)の作り方を示します。0.2mmΦぐらいの細いUEW線(エナメル線でも良いが最近は販売されていない)を3本をよじって、フェライトビーズに4回〜5回巻きます。結線が判りにくくなるのでテスタで後から調べると良いでしょう。ソータバラン(L2)も同じように2本よじって巻きます。
私は図2の回路をすべて空中配線で作りましたが、トランジスタを含むノイズ発生部はもちろんジャノメ基盤等に組んだ方が良いでしょう。ただしブリッジの部分はできるだけ短く配線する必要がありますので、ケースにVRやVC、コネクタを固定してから空中配線にする事をお勧めします。
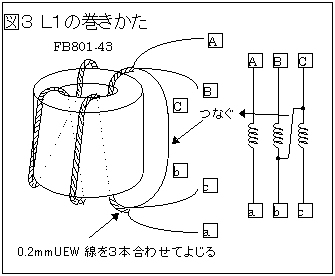
ケースは樹脂性のものを使うと、同軸コネクタを簡単に浮かせることが出来ます。この際、インピーダンス測定用のVRのカバーを、ANT端子のGND側とショートして置くとFBです。少し寄生容量が増えますが、これをしておかないと低い周波数の時にVRに手を近づけるだけで、ノイズヌル点が変化してしまい、使い勝手が著しく悪化します。
完成したら、まずANT端子を短絡しVRを0Ω(左側)にし、適当な周波数を受信機(モードはAM、SSBが良い)で聞いて、VCを適当に回して下さい。ノイズが最小(ヌル)になる点が見つかればブリッジは正しく動作しています。次に校正用に用意した50Ωの抵抗をできるだけ短く同軸オスコネクタにハンダ付けし、ANT端子に接続して、VRを回してノイズヌル点が見つかる事を確認して下さい。この50Ωダミーは、将来共振周波数の測定の際の校正用のダミーとして利用できます。また普段はノイズブリッジのANT端子に接続しておくと紛失する事もありません。Hi
以上で動作確認は完了です。これで一応は完成なのですが、このままでは例えば1.9MHzでのノイズヌル点と、50MHzでのノイズヌル点のVCの位置が微妙に異なると思います。これは内部の部品や配線が持つ寄生容量やインダクタンスが影響しているのが原因です。特にVRの持つインダクタンス分はその位置によって変化するのでやっかいです。これを完全に補償するのは技術的に難かしく、私の手には負えませんので、今回は50Ω付近でのノイズヌル点のVC位置が同じならばOKとしました。
先程作成した50Ωの校正用ダミーをANT端子に接続し、1.9MHz〜50MHzで、VCのノイズヌル点が同じ位置になるように、ノイズブリッジ内部のANT端子と固定コンデンサの間に補償用の適当なインダクタンスを挿入します(図4)。
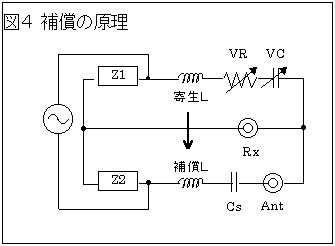
私の場合は約5cmのエナメル線を直列に入れると、VCがだいたい同じ位置でノイズヌル点が得られるようになりました。あまり神経質になるといつまでたっても完成しませんので、適当なところで妥協する事をお勧めします。Hi 納得がいく状態になれば、最終的に空中配線部分をエポキシボンドで固めてしまえばOKです。
○校正
さていよいよ校正です。今回の最大のヤマ場を迎えました。
まずVRから校正します。VRの校正は極めて簡単で、ノイズブリッジのケースを開けた状態でVRの抵抗値をテスターで調べて、適当な間隔で目盛りを刻めばOKです。当初は高周波で校正しようと思ったのですが、私が作成したものでは、HF帯全域で上記の直流抵抗での校正結果と、抵抗をANT端子に接続して、ノイズヌル点を測定した結果がほとんど同じでしたので簡単にすませてしまいました。
次にVCを校正します。
ANT端子に校正用の50Ωダミーを接続します。
ノイズ最小点をノイズブリッジのVCを回して探します。
この位置に∞の目盛りを刻みます。
ここから先は値が判っているリアクタンスが必要です。色々と思案したのですが、できるだけ安上がりな方法という事で、LC直列回路を利用する方法を思い付きました。
まず図5に示すコイルを自作します。このコイルのインダクタンスはなんぼでも構わないのですが、校正用コンデンサとの共振周波数がHF帯に収まるように選んであります。ですから巻き数はかなりええかげんで良く、あまり神経質に作る必要はありません。ただし、校正中に値が大きく変化しないように、できるだけしっかりと作成しビニールテープ等で巻き線を固定して下さい。また密巻きにすると寄生容量が増えますので、スペース巻き(多少ええかげんで良い)にして下さい。塩ビパイプ(VP12)をボビンとして利用すると良いでしょう。
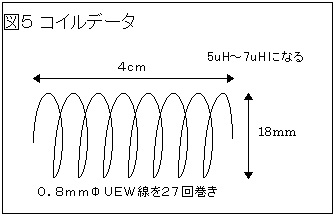
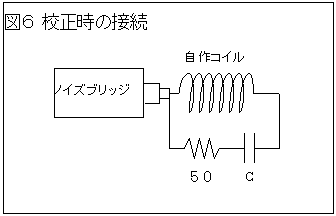
図6に示すように、コイルを同軸オスコネクタの芯にハンダ付けしておき、コンデンサと抵抗は、コイルの逆端とオスコネクタのGND間にハンダ付けして交換します。
ANT端子にコイルと200pF、50Ωを直列に接続します。
VRを50Ωにし、VCを∞位置にします。
5MHz付近を聞いてノイズヌル点になる周波数を探します(VRも微調)。
この周波数が共振周波数です。fsとしてメモに記録します。
fsを0.442719倍した周波数に受信機を合わせます。
VCを回してノイズヌル点を探します(VRも微調)。
この位置に-250の目盛りを刻みます。
上記の5〜7を表1に示す周波数倍率で同様に行います。
ノイズヌル点が見つからない場合は測定範囲外ですので、その位置に目盛りを刻むのはあきらめます。また目盛り間隔が近すぎて刻めない場合は適当に間引いてください。
上記の1〜9を82pFと50Ωで繰り返します(fs=7MHz付近)。
上記の1〜9を10pFと50Ωで繰り返します(fs=20MHz付近)。
ANT端子に10pFと50Ωを直列に接続します(コイルなし)。
VCを回してノイズヌル点を探します(周波数は任意だが低いほうがFB)。
ノイズヌル点が見つからない場合は測定範囲外ですので校正は終了です。
見つかればこの位置に-10の目盛りを刻みます。
上記の校正作業中、最初の共振周波数を求める際に、校正用の50ΩダミーでVCの∞位置を校正しながらやるとより正確に行うことができます。
表1.リアクタンス校正の周波数倍率表
| C = 200[pF] |
C = 82[pF] |
C = 10[pF] |
| 目盛り |
周波数倍率 |
| -250 |
0.443 |
| -300 |
0.574 |
| -350 |
0.652 |
| -400 |
0.705 |
| -500 |
0.773 |
| -600 |
0.815 |
| -800 |
0.865 |
| -1000 |
0.894 |
| 1000 |
1.096 |
| 800 |
1.119 |
| 600 |
1.155 |
| 500 |
1.184 |
| 400 |
1.226 |
| 350 |
1.255 |
| 300 |
1.292 |
| 250 |
1.343 |
| 200 |
1.416 |
| 150 |
1.530 |
|
| 目盛り |
周波数倍率 |
| -90 |
0.279 |
| -100 |
0.412 |
| -120 |
0.555 |
| -150 |
0.668 |
| -200 |
0.765 |
| -250 |
0.817 |
| -300 |
0.850 |
| 300 |
1.130 |
| 250 |
1.154 |
| 200 |
1.190 |
| 150 |
1.246 |
| 120 |
1.301 |
| 100 |
1.353 |
| 90 |
1.386 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| 目盛り |
周波数倍率 |
| -20 |
0.671 |
| -30 |
0.796 |
| -40 |
0.851 |
| -50 |
0.883 |
| -60 |
0.904 |
| -70 |
0.918 |
| -80 |
0.929 |
| -90 |
0.937 |
| 90 |
1.059 |
| 80 |
1.067 |
| 70 |
1.076 |
| 60 |
1.088 |
| 50 |
1.105 |
| 40 |
1.129 |
| 30 |
1.169 |
| 20 |
1.245 |
| 10 |
1.449 |
| |
|
|
マイナス側の目盛りは小さな値まで刻めますが、プラス側はバリコンの最大容量ぐらいまでしか刻めないと思います。
念のために目盛りはエンピツで仮に刻み、時間をおいてもう一度やると単純なミスが発見できます。また校正用の標準コンデンサのみをANT端子に接続し、ノイズヌル点でのVCの読みがその値とだいたい等しくなる事を確認しておくと良いでしょう。もし大きく異なる場合は、上記の校正操作が正しく行われていない事になります。
参考までに周波数倍率を得るための計算式を以下に示します(f/fs=周波数倍率,c=標準コンデンサ,cx=ダイアル目盛り)。表1の計算ではコイルの寄生容量を1pFと見込んでCに加算して計算してあります。
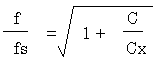
○基本操作
ノイズブリッジの基本的な操作方法を以下に示します。
インピーダンス測定
ANT端子に負荷を接続し、VCとVRを回してノイズヌル点を探します。この時受信機は、目的とする(測定したい)周波数にセットしておきます。
ノイズヌル点を見つけたら、その時のVRの読みが負荷の抵抗、VCの読みが負荷のリアクタンスを表わします。ただし抵抗は目盛り直読そのままですが、リアクタンスについては以下の変換式で求めます。
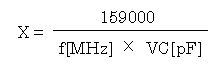
例えば21MHzで目盛りの読みが+300(pF)の時は、
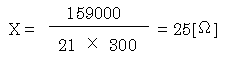
VCの読みがマイナス側の時は、キャパシティブでR−jXとなり、プラス側の時はインダクティブでR+jXになります。
ただし本器でのインピーダンス測定は、VRが50Ωから大きく外れると、周波数が高い程誤差が増えますので、その点を織り込んで評価する必要があります。この場合、リアクタンスに関しては以下の補正計算を行うとより正確になります。
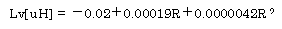
真のリアクタンスXtは、
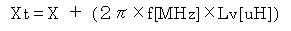
私は2台作成し、VRやVC、ブリッジ回路に違うものを使って色々と実験しましたが、いずれも上記の補正が必要でした。これはVRの回転軸に対する寄生インダクタンスや寄生容量の変化による影響が大きいと思います。ただ補正式はいずれの場合も上記のものでOKでしたので、皆さんが作成されるものも大きくは外れないと思います。
ちなみにVRが0Ω〜100Ωの範囲では、HF帯では実用上は補正の必要はないと思います。また現実のアンテナ調整の際は、こんな補正計算はやってられないので、だいたいの目安として傾向をつかんでおけば十分だと思います。
共振周波数の測定
ANT端子に負荷を接続し、受信周波数を変化させながらノイズヌル点を探します。この時、ノイズブリッジのVCやVRを適当に回しながら探るとすぐに見つける事ができます。
一旦ノイズヌル点を見つけたら、VCの位置が目盛り∞の点でノイズヌル点になるようにVRと受信周波数を更に調整します。
正確に測定したい場合は、この時、一旦ANT端子に校正用に作成した50Ωダミーを接続し、目盛り∞付近でVCを校正(ノイズヌル点を探す)した後、負荷を接続して、VRと受信周波数を探ります。最終的にノイズヌル点となる受信周波数が負荷の共振周波数になります。
スペアナやスペアナ付きの受信機が利用できる場合は、それを受信機として使用して、共振周波数を一発で目視する事ができます。
インピーダンスの測定の場合と同様に、VRが50Ωから大きく外れている場合は、高い周波数ではVC目盛り∞の位置がリアクタンス0点からずれますので、先程示した補正計算でLvを求めて、以下の式でリアクタンス0点のVC目盛りを求めます。
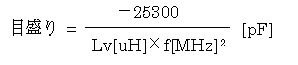
○応用
ノイズブリッジの応用例は多岐にわたり、測定対象もアンテナに限る事はありません。しかしその全てを紹介するのは無理ですので、ここではごく普通のアンテナ関係での使用方法を説明します。
なお、私たちが良く使う定在波型(共振型)のアンテナに、同軸ケーブルで給電する場合は、次の3つのポイントがあります。
目的の周波数で共振させる(Xを0にして純抵抗にする)
インピーダンス(純抵抗)を同軸ケーブルに合わせる
平衡型のアンテナの場合は、平衡−不平衡を変換する
上記の3点は別のものですので、混同しないように注意して下さい。整合法によっては上記の全部が一気に解決する方法もありますので、それが混同され易い原因になっていると思います。
また後ほど詳しく解説しますが、インピーダンスを測定する場合は、その挿入位置を可能な限りアンテナに近い位置にするか、またはアンテナと接続する同軸ケーブルの電気的な長さを測定周波数の1/2λの整数倍長にしておくと問題が発生しません(図7)。
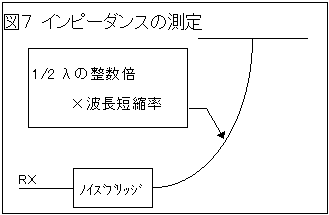
エレメントの調整(共振させる)
目的周波数で基本操作で示したインピーダンス測定の方法をそのまま実践します。得られたRとXが現在のアンテナのインピーダンスになります。
エレメント長を調整する場合、Xを0(共振状態)にするのが普通ですので、私達が良く使うアンテナでは、得られたVCの読みがプラス(インダクティブ)の場合はエレメントを短くし、マイナス(キャパシティブ)の場合はエレメントを長くします。
最終的にVC目盛りが∞の位置でノイズヌル点になるようにエレメントを調整すれば、そのアンテナは目的周波数で共振している事になります。
また別の方法として、基本操作で示した方法で共振周波数を測定し、その結果からエレメントを調整する事もできます。この際、得られた共振周波数が目的周波数よりも高い場合はエレメントを長くし、低ければ短くすれば良いのはご存じの通りだと思います。
この方法のメリットは、アンテナのRが共振周波数で50Ωに近ければ、任意長の同軸ケーブルを介して測定しても良い点です(図8)。
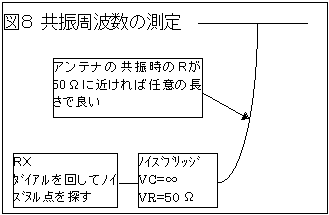
インピーダンス整合(Rの調整)
アンテナが目的周波数で共振した際の純抵抗が、同軸ケーブルのインピーダンスに近ければ、そのまま直結して使用する事ができます(ただしアンテナによっては平衡−不平衡を変換するためのバランは必要)。
例えば、半波長ダイポールは理想的な環境では約75Ω、1λループは約100Ω、バーチカルやホイップは30〜40Ωになる事が知られています。
50Ωケーブルを使用してSWRが1.5以下になる負荷のRの範囲は33〜75Ωですので、多少の相違は実用上問題にならないと思います。
運悪くRが許容範囲を越える場合は、これを同軸ケーブルと整合するための何等かの仕掛けが必要になります。
Rはアンテナ形状や設置環境等で決まる固有のものですので、共振周波数のように簡単には調整できませんが、わざとエレメントを共振からずらしてリアクタンス成分を残留させ、コイル(ヘアピン)や、コンデンサで並列共振回路を作り、見かけのRを高くして整合する方法があります。この代表的な例としては八木アンテナのヘアピンマッチ、モービルホイップの給電部にコンデンサを抱かせる方法等があります。
実は今回のノイズブリッジが最も威力を発揮するのはこのようなケースで、例えば21MHzのモービルホイップを作成した時、アンテナのRが25Ωの時は、エレメントを少し長目にするか又はローディングコイルを調整して、Xが+25Ω(VC目盛りは+300)になるようにします。そして150pFのコンデンサを給電部にパラに入れると50Ωで整合が取れます。50Ωで整合する場合の、アンテナのRに対する抱かせるコンデンサの関係を図9に示します。
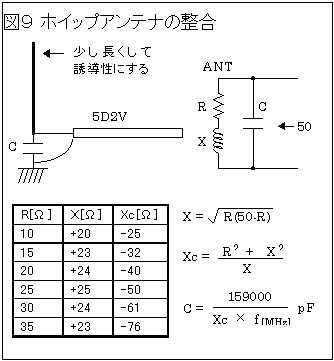
他の整合法としてHF帯ではトロイダルコアを使ったトランスによるインピーダンス変換も良く使われ、また同軸ケーブルを使用するQマッチという方法もあります。
形状そのものを変える整合法としては、逆VやGPの展開角を調整する方法や、八木アンテナで良く使われるガンママッチ等があります。後者の場合は給電エレメントをフォールデットダイポールに置き換えてRを上昇させています。
いずれの整合法でも、ノイズブリッジを効果的に使うことにより、調整作業を簡単にする事ができます。ここで個々のケースについて紹介するのは無理なので、CQ出版の「アンテナ・ハンドブック」等を参照される事をお勧めします。
なお、SWR測定によりアンテナを調整する場合、その共振(リアクタンス0)とRの整合が同時に解決されるような点を探すことになりますので、整合法によっては、その方向性が判らず、かなりの経験を積まないと暗中模索の状態に陥りやすいと思います。
バランの評価
バランのANT側に50Ωの抵抗(1:4の場合は200Ω)を接続し、その逆端(フィーダ側)にノイズブリッジを接続します。使用する周波数でインピーダンスが50Ω(リアクタンス0)付近ならばまずはOKです。さらに、25Ω(1:4の場合は100Ω)の抵抗2本を直列にし、それをバランのANT側に接続し、その抵抗の中点をフィーダ側のGNDと短くショートします。使用する周波数でインピーダンスが50Ω付近ならば、そのバランのアイソレーション(分離度)もOKだと判断できます(図10)。
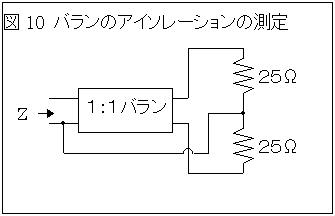
トロイダルコアを使ったバラン(要するにトランス)にはソータバラン(フロートバラン)や、強制バラン等色々な種類がありますが、いずれも上記の方法で評価できます。
なお、水平DPでは強制バラン(ほとんどの市販品はこれ)が良く使われますが、私達の設置環境ではアンテナのほうが、まわりの建物等の影響で理論通りに平衡していないので、ソータバランを使ったほうが良い場合が多いと思います。
同軸ケーブルの特性測定
同軸ケーブルの波長短縮率を求めるには色々な方法がありますが、ここでは1/2λのショートスタブが直列共振状態になるのを利用する方法を紹介します。まずサンプルの同軸ケーブルの長さをメジャーで計ります。あまり短すぎると周波数が高すぎて、このノイズブリッジの測定範囲を越えますし精度も悪化しますので、3m以上あるほうが望ましいでしょう。
次に長さL(m)が1/2λとなる周波数fs=300/(2×L)を計算します。実際の共振周波数は波長短縮率の影響を受けてそれよりも低くなるはずです。
ノイズブリッジにその同軸ケーブルを接続し、先端をショートさせて、fsよりも低い周波数の共振周波数を探します(VR=0,VC=∞)。得られた共振周波数をfとすると波長短縮率は、
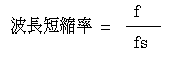
で求める事ができます。
同軸ケーブルがメチャンコ長い場合は、1/2λとせずに1λ等の、1/2λの整数倍とした周波数を探しても良いでしょう。
同軸ケーブルの特性インピーダンスを測定するには、任意長(短すぎると判りにくい)の同軸ケーブルの先端に500Ω程度のVRを接続し、任意の周波数でノイズブリッジのVRと、先端のVRの両方を調整してノイズヌル点を探します(VCは∞位置)。この時、周波数を可変させてもノイズヌル点が変化しなくなるまで両方のVRを調整し、最終的に得られたVR(どちらのVRも同じ値になっているはず)の読みが同軸ケーブルの特性インピーダンスになります。
同軸ケーブルの減衰量を測定するには、電気長1/2λの整数倍(短いと測定は困難)の長さで先端を短絡し、そのインピーダンスを測定します。減衰がなければRは0Ωになるはずですが、減衰があると表2のような値になります(Rは50Ωケーブルと75Ωケーブルで異なります)。
表2.ケーブルの減衰量の目安
| 減衰 |
R(50) |
R(75) |
SWR |
| 0dB |
0 |
0 |
∞ |
| 1dB |
6 |
9 |
8.72 |
| 2dB |
11 |
17 |
4.42 |
| 3dB |
17 |
25 |
3.01 |
| 4dB |
22 |
32 |
2.32 |
| 5dB |
26 |
39 |
1.92 |
| 6dB |
30 |
45 |
1.67 |
ローディングコイル
HF用のベランダアンテナやモービルホイップでは必ずと言ってよいほどローディングコイルのお世話になります。この際、自作したローディングコイルのインダクタンス(L)が知りたい場合が良くあります。
まずそのコイルの分布容量を調べます。値が判っているコンデンサ2個(C1,C2[pF])を用意し、50Ωの抵抗と測定するコイルを直列に接続し(校正の時に行ったのと同じ)、それぞれの共振周波数(f1,f2[MHz])を求めます。分布容量(Cd[pF])は、
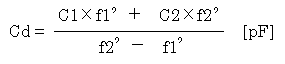
で求まります。コイルのインダクタンス(L[uH])は、
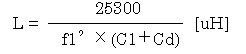
で求める事ができます。ノイズブリッジの50Ω付近の精度が最も良いために、直列に50Ωの抵抗を入れていますが、これはなくても結果はそう大きくは変わらないと思います。また小さなコイルの場合は分布容量も小さいので、C1が大きければ、その補正を省略しても構いません。
SWRの計算
ノイズブリッジは直接SWRを測定する事はできませんが、得られた負荷のインピーダンスRとXからSWRを計算で求める事ができます。以下に計算式を示します(Zoはフィーダのインピーダンス)。

リアクタンス成分がない(X=0)場合は、更に次のような単純な計算で求める事ができます。
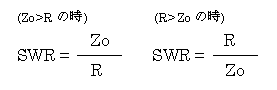
○フィーダについて
同軸ケーブル等のフィーダは分布定数線路と呼ばれ、先端に接続された負荷のインピーダンスと線路のインピーダンスが整合していない場合、様々な問題を引き起こします。インピーダンスを測定する場合は、この事を注意深く検討しておく必要があります。
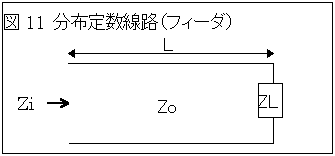
図11のような分布定数線路(フィーダ)の先端に負荷(アンテナ)ZLを接続した時、フィーダの入力端から見たインピーダンスZiは、フィーダのインピーダンスをZoとすると、次の式で得られる事が知られています(フィーダは無損失と仮定)。
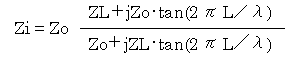
この式からZo=ZLの時(整合状態)、分数部分が常に1になり、Ziはフィーダの長さに関係なくZoになる事が判ります。この状態こそ私達が理想とする状態で、現実には完璧とはいかないまでも実用上問題ない程度にZLを追い込んで使用する事になります。
問題は負荷ZLがZoと等しくないケースで、どのようになるかを計算した結果を表3に示します。
表3 フィーダ長とインピーダンスの関係(Zo=50Ω)
| 長さ |
負荷
50Ω(整合状態) |
負荷
25Ω |
負荷
50+j300Ω |
| L(λ) |
R |
jX |
SWR |
R |
jX |
SWR |
R |
jX |
SWR |
| 0.0 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
25.00 |
0.00 |
2.00 |
50.00 |
300.00 |
37.97 |
| 0.1 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
33.74 |
24.07 |
2.00 |
6.47 |
-98.72 |
37.97 |
| 0.2 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
77.73 |
34.27 |
2.00 |
1.66 |
-25.69 |
37.97 |
| 0.3 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
77.73 |
-34.27 |
2.00 |
1.35 |
7.72 |
37.97 |
| 0.4 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
33.74 |
-24.07 |
2.00 |
2.61 |
49.55 |
37.97 |
| 0.5 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
25.00 |
0.00 |
2.00 |
50.00 |
300.00 |
37.97 |
| 0.6 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
33.74 |
24.07 |
2.00 |
6.47 |
-98.72 |
37.97 |
| 0.7 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
77.73 |
34.27 |
2.00 |
1.66 |
-25.69 |
37.97 |
| 0.8 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
77.73 |
-34.27 |
2.00 |
1.35 |
7.72 |
37.97 |
| 0.9 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
33.74 |
-24.07 |
2.00 |
2.61 |
49.55 |
37.97 |
| 1.0 |
50.00 |
0.0 |
1.00 |
25.00 |
0.00 |
2.00 |
50.00 |
300.00 |
37.97 |
この計算結果からも判るように、負荷ZLがZoと等しくない時、Ziでインピーダンスを計測しても、ほとんどの長さで正しい結果が得られない事が判ります。また長さによってはリアクタンスの符号が反転し、エレメントの調整方向の判断を誤る場合がある事も判ります。
唯一フィーダの長さが計測周波数波長の0.5λ(1/2λ)の倍数の時、Zi=ZLとなり、負荷のインピーダンスを正しく計測する事ができます。
またはフィーダの長さが判っている場合は、測定したZiからアンテナのZLを逆算する事ができます。マルチバンドのアンテナではフィーダの長さを1/2λの倍数にできないのでこの方法を使います。参考までに計算式を示します(減衰量は無視しています)。
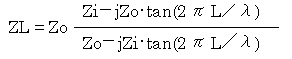
この計算は複素数を含んでいるので電卓や計算尺では気が狂いそうになります。昔はスミスチャートを利用しましたが、使い方をすぐに忘れる(Hi)ので計算機を利用すると便利です。
なお、長さLやλはフィーダの波長短縮率(5D2V=0.67,5DFB=0.81等)の影響を受けますので、物理的な長さは電気長にそれを掛ける必要があります。
以上の事から、アンテナを設置する場合は、フィーダの電気長は可能な限り使用周波数の1/2λの整数倍にしておくと便利な事が判ります。また最悪でもフィーダの長さを計っておくとアンテナ側のインピーダンスが計算できます。ただしHFの場合はフィーダの損失は無視できますが、周波数が高くなるとそれも無視できなくなりますので更に計算が複雑になります(こんな時こそ計算機の出番ですHi)。
ここで表3の計算結果のSWRに注目すると、先端の負荷が同じならば、フィーダの長さに関係なくSWRは等しい事が判ります(SWRの定義が入射波と反射波の比なので当然なのですが...)。つまりフィーダが無損失の場合はCM型のSWRメータを使う場合、どの部分に挿入しても同じ値を示すはずで、「フィーダの長さを変えてSWRを追い込む」という俗説は誤り(不可能)という事になります。
ところが送信機(SWR計)とフィーダの特性インピーダンスが異なる場合は事情が変わります。75Ωケーブルに120Ωの負荷を接続し、ケーブルの長さを変化させた場合に50Ωで給電するとどうなるかを表4に示します。
表4.75Ωケーブルに50Ωで給電
| L(λ) |
R |
jX |
SWR(50) |
| 0.00 |
120.00 |
0.00 |
2.40 |
| 0.05 |
104.44 |
-29.93 |
2.31 |
| 0.10 |
77.97 |
-36.15 |
2.05 |
| 0.15 |
59.38 |
-27.53 |
1.69 |
| 0.20 |
49.77 |
-14.26 |
1.33 |
| 0.25 |
46.88 |
0.00 |
1.07 |
| 0.30 |
49.77 |
14.26 |
1.33 |
| 0.35 |
59.38 |
27.53 |
1.69 |
| 0.40 |
77.97 |
36.15 |
2.05 |
| 0.45 |
104.44 |
29.93 |
2.31 |
| 0.50 |
120.00 |
0.00 |
2.40 |
ケーブル長を0.25λ(1/4λ)にした場合に、インピーダンスは50Ωに近づきSWRも十分に低い値です。この先に50Ωのフィーダを接続し任意長の長さで引っ張っても良さそうです。
この方法はQマッチと呼ばれるインピーダンス整合法として実際に使われています。
また表3に示したようにフィーダ上のインピーダンスが様々に変化するのを逆に利用したスタブマッチと呼ばれる整合法もあります(図12)。
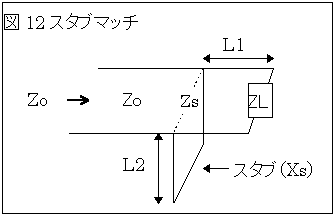
これはフィーダ上のL1点でのインピーダンスZsと、そこに並列に接続するスタブ(L2)のリアクタンスXsの合成インピーダンスがフィーダのインピーダンスZo(純抵抗)と等しくなるようにL1とL2を決める方法で、前に紹介したホイップアンテナの整合と本質的には同じ原理です。フィーダとスタブの損失が小さい場合は、負荷が非共振で多少のリアクタンスがあっても問題ありません。ZLをノイズブリッジで測定すれば、L1とL2はスミスチャートや計算機を使って簡単に求める事ができます。スタブの代わりにコイルやコンデンサを使っても良いですが、スタブのほうが損失の少ないリアクタンスを容易に得やすいので、この方法が良く使われます。
○ おまけ
今回このノイズブリッジを実験中に、現在ベランダに設置している磁界型ループアンテナに(同軸ケーブルを介してリグ側に)接続してみました。いろいろと試しているうちに、ノイズブリッジのVRを50Ω、VCを∞に固定して、ループアンテナのリモートコントローラを調整すると、簡単にノイズヌル点を見つける事ができるのを発見しました。もちろんその状態で無線機に接続しなおして送信するとSWRは1:1で即使用可能です。
いつもこのアンテナを使う場合は、送信してSWRを見ながらリモートコントローラでチューンを調整する必要があり、その際かなり気を使っていましたので嬉しい発見でした。
幸い私の使っているFT1000MPには、外部プリセレ用のRxOutとRxInのコネクタが出ており、Rig側のパネルSWで簡単に切り替える事ができます。そこで図13のような専用のブリッジを作成し、この間に入れておくと、受信だけで完璧にチューンが取れるようになりとても便利になりました。
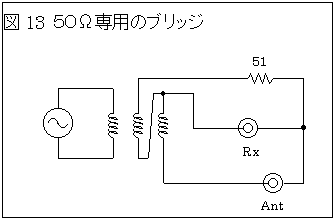
○さいごに
今回の製作を通じて、高周波回路の奥の深さを改めて感じました。HF帯ではあまり問題にならない配線や部品のリアクタンス成分が、50MHzでは相当効いてくるのが実感できます。私の場合はHF帯が主ですのでこの点でかなり妥協しましたが、腕に自信がある方はぜひこの点もクリアしてみて下さい(その時は教えてね!)。
最後になりますが、今回貴重な会報のページを割いて頂き有り難うございました。またJA3ATJ坂井OMに、編集作業や誌面の割り振りで大変なご苦労をおかけしました。この場をお借りしてお礼申し上げます。有り難うございました。
73
○参考文献
* 山村英穂「トロイダルコア活用百科」S58
初版 CQ出版
* 角居洋司,吉村裕光「アンテナ・ハンドブック」
1993 第13版 CQ出版
* 古谷恒雄「空中線系および電波伝搬」1976
啓学出版